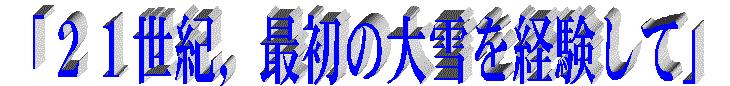~国際ワークショップを長岡で開催~
~国際ワークショップを長岡で開催~
国際ワークショップ『21世紀、最初の大雪を経験して』-基調講演と事例交流-
日 時: 2001年9月20、21日
場 所: 長岡市立中央図書館 2F講堂、講座室
長岡市学校町1丁目2番2号 TEL.0258-32-0658
主 催: 独立行政法人 防災科学技術研究所 長岡雪氷防災研究所
共 催: 新潟県,長岡市
後 援: (社)日本雪氷学会,(社)日本雪氷学会北信越支部
|
国際ワークショップ
-基調講演と事例交流-
21世紀最初の冬は,モンゴルやロシアなど世界各地からの雪や寒冷の被害がニュース等で話題となりました.また,国内でも10数年ぶりの大雪となり,除雪等の雪処理や吹雪,雪崩,スリップ等の交通事故による災害に悩まされた自治体も多い冬でありました.
大規模な雪の害は,毎年発生するものではありません.このため,久しぶりの雪氷害に対処するためには,経験の蓄積,情報の交換及びそれを風化させずに継承することが必要です.
本ワークショップは久しぶりの大雪となった「21世紀最初の大雪」をテーマとして,国内外の第一線の研究者による基調講演と雪氷関連実務担当者による情報交換の場を提供するとともに,雪氷災害を我が国だけの特殊な問題として閉じ込めることなく,広く,また違った角度から考えることを目的とし,開催致しました.
| プログラム |
| |
| 【9月20日】 |
| 9:30~10:00 |
開会式 |
| 10:00~11:00 |
海外事例紹介Ⅰ 今冬のモンゴルの大雪害 ゲレクピル・アディアバダム (モンゴル自然環境省 気象・水文研究所) |
| 11:15~12:15 |
基調講演Ⅰ 近年の日本の暖冬傾向を北半球の気象から考える 中村 尚 (東京大学大学院理学研究科) |
| 13:00~15:00 |
事例紹介コアタイム |
| 15:00~16:00 |
国内事例発表Ⅰ |
| 16:00~17:00 |
海外事例紹介Ⅱ 最近のシベリア・ヤクーツクの大洪水について ウラディミール・ソロヴィエフ (ロシア科学アカデミー 航空・宇宙物理研究所) |
| 【9月21日】 |
| 9:00~11:00 |
国内事例発表Ⅱ |
| 11:15~12:15 |
基調講演Ⅱ 日本海降雪雲のメカニズムとその人工調節技術の現状 村上 正隆 (気象庁気象研究所 物理気象研究部) |
| 13:00~15:00 |
意見交換及び閉会 |
本ワークショップは自治体の雪氷関連実務担当者等による情報交換としての国内の事例発表(口頭発表9件、パネル展示17件)および、国際的な視点での外国人研究者による海外での雪氷、寒冷害の事例紹介(2件)を行なうとともに、このような大雪を生み出す気候・気象のメカニズムに関連した基調講演(2件)を行ないました。本ワークショップには2日間で合わせて190名の実務担当者、研究者、一般市民が参加しました。
基調講演では、東京大学の中村尚氏から、近年の暖冬傾向が北半球規模の大気循環変動に伴うものであり、今回が大雪であるとはいえ全体としては暖冬傾向の中にあること、また現在が暖冬傾向だからといって豪雪は2度と来ないとはいえないことが説明されました。気象研究所の村上正隆氏からは集中豪雪をもたらす擾乱の構造・メカニズム、および気象モデルを用いた人工降雨・降雪技術の研究の現状についての紹介がなされました。
また、海外からの2講師による事例紹介では、日本では考えられないようなモンゴルとロシアの災害事例が紹介されました。モンゴル自然環境省気象・水文研究所のゲレクピル・アディアバダム氏からはゾッドゥと呼ばれる災害について紹介されました。ゾッドゥ災害はモンゴルにおける冬の寒冷や降雪、夏の水不足による家畜の被害をもたらす災害で、最近の2冬期に起こったゾッドゥ災害により大量の家畜が失われ、カシミア産業に多大の損害が及びました。ロシア科学アカデミー航空・宇宙物理研究所のウラディミール・ソロヴィエフ氏からはロシアのヤクート共和国において、今冬の厳しい寒さにより凍結した河川が、春期に増水して洪水被害をもたらしたことについての報告がなされました。
国内事例紹介では福井、金沢、富山等での今冬の大雪の情況や各自治体の対応等について口頭発表があり、またパネル展示では90分問のコアタイムが熱い議論であっという間に過ぎてしまいました。最後の意見交換の中で、今後ともこのような情報交換の場が一般市民を含めてもっと多くの参加者を巻き込んで続けられるようにとの意見も寄せられ、2日間に渡るワークショップは閉会しました。
 ~国際ワークショップを長岡で開催~
~国際ワークショップを長岡で開催~ ~国際ワークショップを長岡で開催~
~国際ワークショップを長岡で開催~