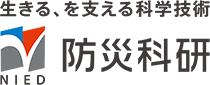イベント情報
第5回防災科学技術研究所成果発表会
日時
平成18年6月13日(火曜) 10時00分~17時00分
会場
つくば国際会議場(エポカルつくば)
(茨城県つくば市竹園2-20-3)
参加申し込み
事前受付を締め切らせていただきました
当日の参加受付も致しますのでふるってご参加下さい
プログラム
- 10時00分~10時10分
-
開会挨拶
文部科学省 - 10時10分~10時30分
-
今中期計画における研究開発方針
理事長 岡田義光
第1部 火山・気象・雪氷等の災害軽減に向けて
- 10時30分~10時55分
-
火山災害の軽減を目指して ー噴火予知と災害予測ー
火山防災研究部 鵜川元雄 - 10時55分~11時20分
-
1時間先の豪雨災害の発生予測を目指して ーマルチパラメータレーダの利用ー
水・土砂防災研究部 眞木雅之 - 11時20分~11時45分
-
雪害を減らす ー雪氷災害発生予測システムの開発ー
雪氷防災研究センター 佐藤篤司 - 11時45分~12時10分
-
災害に強い社会システムの形成に向けて
防災システム研究センター 佐藤照子 - 12時10分~14時10分
-
休憩
- 12時10分~14時10分
-
ポスター展示・システムのデモンストレーション(コアタイム)
つくば国際会議場大会議室101、中ホール300周辺スペースにおいて約70点を出展
特別講演
- 14時10分~15時00分
-
日本アイ・ビー・エム社における災害への備えと顧客のシステムの復旧対応 ー災害現場からの報告ー
(日本アイ・ビー・エム 執行役員 白川一敏) - 15時00分~15時15分
-
休憩
第2部 地震災害軽減への挑戦
- 15時15分~15時40分
-
基盤的地震観測網を活用した地震活動の評価
地震研究部 堀 貞喜 - 15時40分~16時05分
-
地震ハザード評価手法の開発
防災システム研究センター 藤原広行 - 16時05分~16時30分
-
E-ディフェンスを活用した耐震工学研究
兵庫耐震工学研究センター 松森泰造 - 16時30分~16時55分
-
自治体のための災害対応情報システムの開発
防災システム研究センター 後藤洋三 - 16時55分~17時00分
-
閉会挨拶
理事 小中元秀
参加費
無料(懇親会は¥1,000)
定員
324名
成果発表会ポスター
講演詳細
第1部 火山・気象・雪氷等の災害軽減に向けて
- 「火山災害の軽減を目指して -噴火予知と災害予測-」 (鵜川 元雄)
-
噴火予知と噴火後に発生する災害の予測によって、火山災害の被害、特に人的犠牲は、大きく軽減することができます。当研究所では、これまで噴火予知技術の向上のための研究を進め、例えば2000年三宅島噴火ではマグマの動きを把握することができました。今後は把握から予測につながる研究に発展させるとともに、溶岩流や火砕流など、災害要因の予測の研究も計算機によるシミュレーションを活用して進めていきます。
- 「1時間先の豪雨災害の発生予測を目指して -マルチパラメータレーダの利用-」 (真木 雅之)
-
従来、気象レーダから推定した雨量は誤差が大きいために地上の雨量計による補正が必要と言われていましたが、当研究所が開発したマルチパラメータレーダ(MPレーダ)により、レーダだけで正確な雨量分布を500m間隔、1分間隔で測定することに成功しました。MPレーダ用いた降雨量推定についての研究成果と、MPレーダ情報を用いた豪雨災害の発生予測手法についての今後の研究計画を紹介します。
- 「雪害を減らす - 雪氷災害発生予測システムの開発 -」 (佐藤 篤司)
-
今冬は全国的に強い寒波、豪雪が襲い、家屋の倒壊、雪崩災害、高齢者の除雪中の事故等が多発し、「平成18年豪雪」となりました。毎年起こるこれらの雪害を軽減するため、降雪予測、積雪変質予測を基に雪崩や吹雪の発生、道路雪氷状況を予測するモデルを連結し「雪氷災害発生予測システム」のプロトタイプを構築しました。雪崩で交通規制を行った国道沿線での試験的運用など、雪害発生の危険度予測の実用化に一歩前進しました。
- 「災害に強い社会の形成に向けて」 (佐藤 照子)
-
災害リスク研究チームでは、水害に対する住民の関心を高める方策や、社会と個人の双方が協働して災害リスクを管理するという新しい考え方による「災害リスクガバナンス」の手法を確立するための研究を、自然科学者と人文・社会学者のチームで研究しています。そして、研究成果をもとに、その根幹であるリスクコミュニケーションを支援する社会インフラとして「参加型水害リスクコミュニケーション支援システム(Pafrics)」を開発し、公開しました。
特別講演
- 日本アイ・ビー・エム社における災害への備えと顧客のシステムの復旧対応:災害現場からの報告 (日本アイ・ビー・エム(株) 執行役員 白川一敏)
-
グローバル企業であるアイ・ビー・エム社における災害発生時の対応について、「阪神・淡路大震災」等の災害経験にもとづき、顧客に対するシステム復旧サービスや将来の災害発生への備え等に焦点をあててご講演していただきます。
第2部 地震災害軽減への挑戦
- 「基盤的地震観測網を活用した地震活動の評価」 (堀 貞喜)
-
阪神・淡路大震災後に始まった基盤的地震観測網の整備事業は、この5年間で当初の目標をほぼ達成することができました。これにより、私たちの足下で起きている地学現象を大変詳しく把握できるようになりました。観測データを詳細に調べることにより、通常の地震活動に加え、プレート間のゆっくりすべりや低周波微動活動などさまざまな地学現象が明らかとなっており、今後の地震発生予測に向けた展望が大きくひらけてきました。
- 「地震ハザード評価手法の開発」 (藤原 広行)
-
「全国を概観した地震動予測地図」が完成し、地震調査研究推進本部地震調査委員会から公表されました。当研究所では、予測地図の作成のため、強震動予測手法や確率論的地震ハザード評価手法の研究を行い、予測地図作成作業を行ってきました。さらに、作成の前提条件となったデータも併せて、予測地図を「地震ハザードの共通情報基盤」として公開するために、「地震ハザードステーションJ-SHIS」を開発し、運用を開始しました。
- 「E-ディフェンスを活用した耐震工学研究」 (松森 泰造)
-
構造物の安全性を現実的に検証できる世界で唯一の実験施設として「実大三次元震動破壊実験施設(通称:E-ディフェンス)」が完成し、平成17年4月から本格稼働しました。兵庫耐震工学研究センターでは、地震災害による被害の軽減に資することを目標にE-ディフェンスを活用した耐震工学研究を遂行しており、平成17年度は「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」による「木造建物実験」「鉄筋コンクリート建物実験」「地盤・基礎実験」を実施しました。
- 「自治体のための災害対応情報システムの開発」 (後藤 洋三)
-
首都圏直下地震など大災害による被害を軽減するためには、自治体の災害対応力向上が不可欠です。川崎ラボラトリーは、被害推定と災害対応行動予測の技術により自治体の防災計画や災害時意志決定を支援するシステムと、災害対応に不可欠な災害時の情報共有を実現するプラットフォームの研究・開発を行ってきました。そして、自治体を試験フィールドとしてそれらの防災力支援技術について実証的研究を組織的に進めています。
ポスターセッション詳細
A地震観測データを利用した地殻活動の評価及び予測に関する研究
- A1
-
防災科学技術研究所基盤的地震観測網
- A2
-
高感度地震観測網(防災科研Hi-net)
- A3
-
広帯域地震観測網(防災科研F-net)
- A4
-
強震観測網(K-NET・KiK-net)
- A5
-
深部低周波微動・スロースリップの発見
- A6
-
超低周波地震の発見
- A7
-
地震波が伝える西南日本下のプレート形状
- A8
-
相似地震によるプレート運動モニタリング
- A9
-
断層の構造と応力・強度 ードリリングによるアプローチー
- A10
-
兵庫県南部地震の発生メカニズムを探る
B地震動予測・地震ハザード評価の高度化に関する研究
- B1
-
確率論的地震動予測地図
- B2
-
震源断層を特定した地震動予測地図
- B3
-
地震ハザードステーション J-SHIS
- B4
-
強震動シミュレータ: GMS
- B5
-
統合化地下構造データベースの構築
Cリアルタイム地震情報の高精度化に関する研究
- C1
-
高度即時的地震情報伝達網実用化プロジェクト
- C2
-
緊急地震速報の利活用システム
- C3
-
緊急地震速報のための震源決定
- C4
-
緊急地震速報のための新しい震度推定方法
- C5
-
震源の面的広がりを瞬時に推定するためのアルゴリズム開発
- C6
-
緊急地震速報利活用の自治体・企業における実証実験
D実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を活用した耐震工学研究
- D1
-
実大三次元震動破壊実験施設
- D2
-
E-ディフェンス・サポートツール(地震動データベース&震動台シミュレーション)
- D3
-
地震による木造住宅の倒壊防止に向けた実大実験
- D4
-
巨大地震が構造物の足もとを壊す E-ディフェンスによる地盤基礎実験
- D5
-
震度Ⅶへの挑戦 ー鉄骨建物耐震実験ー
- D6
-
都市の生命線を守る ー橋梁耐震実験研究ー
- D7
-
実大三次元震動破壊実験シミュレーションシステム
E地震防災フロンティア研究
- E1
-
自治体ニーズを反映する実践的研究事例 り災証明書発行システムを用いた災害対応支援
- E2
-
IT(情報技術)を活用した自治体の危機管理
- E3
-
医療システムの防災
- E4
-
リモートセンシングによる災害状況の把握
- E5
-
「現場への適用戦略」による防災研究の革新 ーEqTAPプロジェクト(1999-2004)からの提言ー
- E6
-
災害軽減技術の国際情報基盤の形成
- E7
-
震災総合シミュレーションシステムの活用
- E8
-
情報共有による自治体の減災に関する実証的研究
F火山噴火予知と火山防災に関する研究
- F1
-
火山噴火予測システムの開発へ
- F2
-
富士山の噴火予知に挑む
- F3
-
火山観測網がとらえた2000年三宅島噴火
- F4
-
航空機搭載型スペクトルスキャナによる火山観測
- F5
-
火山観測のための航空機搭載型スペクトルスキャナの開発
- F6
-
宇宙からみた大地の動き
- F7
-
スパコンでせまる噴火のダイナミックス
G気象災害・土砂災害による被害の軽減に関する研究
- G1
-
台風災害の長期変動予測
- G2
-
MPレーダ雨量を用いた都市域のリアルタイム浸水被害危険度予測(あめリスク・ナウ)
- G3
-
MPレーダネットワークによる豪雨・強風の監視と降水短時間予測
- G4
-
土砂災害発生予測支援システム(Lapsus)
- G5
-
地すべり災害の発生予測
- G6
-
降雨と土砂災害 -地中のダイナミックな現象が災害を引き起こす-
H雪氷災害の軽減に関する研究
- H1
-
豪雪はおそろしい -今冬の積雪と雪害-
- H2
-
雪はどこに降るのか?-降雪の分布と予測-
- H3
-
冬道はこんなに危険 -路面状態・路面摩擦を予測する-
- H4
-
雪崩はいつ、どこで起こるか?-雪崩発生予測に挑む-
- H5
-
ホワイトアウトの恐怖にあわないために-吹雪とそれによる視程障害を予測する-
- H6
-
雪氷環境を再現する -雪氷防災実験棟-
M地域防災力向上に資する災害リスク情報の活用に関する研究
- M1
-
住民の災害リスク認知と防災意識
- M2
-
参加型水害リスクコミュニケーション支援システム(Pafrics)
- M3
-
災害リスクコミュニケーション手法の開発 ~地域の安全についての取り組みを活性化するために~
- M4
-
地域防災力向上に資する災害リスク情報の活用に関する研究 ~災害リスクガバナンス研究~
J自然災害情報のデータベース化に関する研究
- J1
-
地すべり地形分布図データベース
- J2
-
新潟県中越地震で生じた斜面変動の詳細分布図
- J3
-
日本の火山ハザードマップデータベース
- J4
-
台風災害情報データベース
- J5
-
沿岸災害危険度マップ
K防災科学技術研究所の国際貢献
- K1
-
防災科研における国際貢献
- K2
-
インドネシアとフィジー・トンガにおける地震観測
- K3
-
エクアドルとの火山観測研究に関する国際協力
- K4
-
ハリケーンカトリーナによる災害調査 ーニューオーリンズ周辺の被害状況ー
- K5
-
2004年インド洋巨大地震・津波国際会議 Part2 災害軽減科学技術の国際連携への提言
L自然災害・防災に関する情報の収集・加工・発信
- L1
-
災害・防災情報の収集と発信
- L2
-
子どもたちへの情報発信