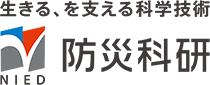防災科研ニュース
バックナンバーリスト(第4期)
バックナンバーは、下記リストからご覧になりたい号数をクリックして下さい。
-
No.220(2023年)令和4年度成果発表会/第4期中長期計画総括
(3.9MB)
特集記事
- 国難級災害を乗り越えるために 2023「情報でつなぎ、災害対応を変える。」
- 第1部 最新の研究成果紹介
- 第2部 研究者一人ひとりによる研究成果発表 表彰
- 第3部 パネルディスカッション
- 地震津波防災研究部門「地震津波予測技術の戦略的高度化」
- 火山防災研究部門「多角的火山活動評価に関する研究」
- 地震減災実験研究部門「社会基盤の強靭性の向上を目指した研究開発」
- 水・土砂防災研究部門「マルチセンシングに基づく水災害予測技術の開発」
- 雪氷防災研究部門「雪氷災害の発生状況およびプロジェクト研究の概要と今後の展望」
- マルチハザードリスク評価研究部門「ハザード・リスク評価に関する研究」
- 防災情報研究部門「情報共有・利活用研究の成果と展開」
- 災害過程研究部門「社会のレジリエンス向上のために」
-
No.219(2022年)先端的研究施設の利活用/今期の災害
(3.3MB)
特集記事
- 災害と向き合い利用者本位の実験研究施設になる
- E-ディフェンスの可能性を信じて
- どんな雨でも安心して生活できるために
- 雪氷防災実験棟を活用した先進的研究の推進に向けて
- 数値震動台の開発とデジタル技術を駆使した都市の災害予測の構想
- 技術で実験研究施設を支える職員の声
- 2022年トンガの火山噴火による特異な津波
- 台風災害情報の集約と発信
-
No.218(2022年)「ハザード・リスク」情報を支える科学技術
(3.4MB)
特集記事
- ハザードとリスク
- 地震動予測地図はどう作られるか
- 地震ハザードステーション J-SHISの開発
- 津波ハザードステーション J-THISとは
- 大地震発生直後に被害を推定する
- 航空写真とAIを用いた建物被害の自動抽出
-
No.217(2022年)火山研究推進センター
(2.0MB)
特集記事
- 火山研究推進センターが目指していること
- 火山観測データの一元化で何が可能になったか
- リモートセンシングによる火山観測技術の開発
- シミュレーションで噴火ハザードを予測する
- 情報ツールで火山災害を軽減させる
- 火山機動観測で火山研究を推進する
-
No.216(2022年)令和3年度成果発表会
(3.6MB)
特集記事
- 「来るべき国難級災害に備えて 2022」令和3年度成果発表会
- 令和3年度成果発表会 来るべき国難級災害に備えて 2022 ~国難にしないために~ モノで守り、行動を変える。
- 第1部 ノイズデータがお宝になる。
- 第2部 研究者一人ひとりによる研究成果発表
- 第3部 発表/パネルディスカッション 国難にしないために~モノで守り、行動を変える。
-
No.215(2021年)今期の災害について
(4.1MB)
特集記事
- 災害の状況を把握する「情報プロダクツ」の開発に向けて
- 線状降水帯の高精度予測
- 衛星画像を用いた斜面変動範囲の抽出
- 現場が本当に求めているのは何か
- 『地理と気象情報』で防災教育を広げる
- 保守・点検の大敵は自然と日々進歩する技術?
-
No.214(2021年)防災科研の地震津波観測研究
(2.1MB)
特集記事
- 防災科研の地震津波観測研究 ~東北地方太平洋沖地震から10年の成果~
- AIと物理モデルのハイブリッドで地震の揺れを予測する
- 極値統計解析に基づく余震による揺れの予測
- 地震発生の理解に向けたS-net津波計の活用
- S-netが捉えた日本海溝のスロー地震
- 記録紙からよみがえる過去のスロー地震
-
No.213(2021年)夏に考える雪氷災害 2020-21年冬期の大雪災害と研究
(5.7MB)
特集記事
- 集中的な大雪に対応するために取り組むべき研究とは
- 今冬の雪氷災害と防災科研の取組
- 今冬の豪雪と雪氷災害情報プロダクツによる発信
- 降水粒子特性が関与する雪氷災害と実況把握のための降水粒子観測
- 雪氷防災研究部門の今後の展開
-
No.212(2021年)令和2年度成果発表会「来るべき国難級災害に備えて2021」
(2.8MB)
特集記事
- 令和2年度成果発表会「来るべき国難級災害に備えて2021」 コロナ禍に対応した新しいイベントへ
- 第1部 講演 ぜひ使ってほしい、防災科研の新たな情報プロダクツ
- 第2部 研究者による成果発表動画ベスト10 発表
- 第3部 パネルディスカッション「東北地方太平洋沖地震」の教訓を南海トラフ地震へ
-
No.211(2020年)防災科研の災害対応-これまでとこれから-
(2.6MB)
特集記事
- 防災科研の災害対応-これまでとこれから-
- 防災科研の災害対応を振り返る
- SIP4Dのこれまでとこれから
- 進化する情報プロダクツ研究
- 災害時に必要な情報がわかりやすいインターフェースへ
- 災害対策本部における現地支援活動
- 防災科研の災害対応に対する体制構築と外部連携
- 防災科研の災害対応のこれから
-
No.210(2020年)イノベーション共創本部
(1.7MB)
特集記事
- イノベーション共創本部がめざすもの
- イノベーション共創本部、始動
- イノベーション共創本部に活かす気象ハブの成果と課題
- 次の国難地震に向けた共創の必要性
- SIP の産学官連携の取組を共創本部に活かす
- 「知の統合」による地域レジリエンスの強化
- 共創の推進に向けて
-
No.209(2020年)南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)の開発・整備
(5.0MB)
特集記事
- 国難級の災害を乗り越えられる社会のレジリエンスを~南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)の開発・整備にあたって~
- 南海トラフ海底地震津波観測網N-net
- N-net の地震津波データ活用に向けて
- 地域防災を支える海域観測網利活用に向けて
-
No.208(2020年)令和元年度成果発表会
(2.4MB)
特集記事
- 「知る、備える、行動する」~最近の広域大規模風水害に学ぶ~
- オリンピック・パラリンピックにも貢献! 30分先までの大雨をピンポイントで予測
- 大雨の希さから危険を知る
- ハザードからリスクへ! リアルタイムに洪水・土砂災害リスクを知る
- 衛星データから被災状況を早く知る
- SIP4D で災害情報を共有する
- 水害に強いすまいを考える
- 特別対談レポート:「避難~災害を乗り越えるための行動をどう促していくか~」
-
No.207(2019年) 今期の災害について
(1.9MB)
特集記事
- 防災科研の「宝」を「力」にする。~防災の知の拠点~
- データ同化技術に基づくリアルタイム地上風速推定手法の紹介
- 宮城県における令和元年台風第19号
- 令和元年台風第 19 号による関東平野の被害概況
- 宇宙から被災状況を把握して災害対応へ活かす
- 過去のデータが教えてくれる災害が起こる可能性
- 2019 年の ISUT による災害対応と N²EM
-
No.206(2019年) 気象災害軽減イノベーションセンター
(2.6MB)
特集記事
- 想定外をなくす行動イノベーションによるレジリエンス強化
- 「攻めの防災」に向けた気象災害軽減イノベーションセンターの取り組み
- 気象災害軽減イノベーションセンターが構築した新しい仕組み
- 知と人をつなげて「共に創る」を実現する
- 気象ハブにおける多様な人材育成と人材と技術の糾合
- 大雪対応サプライチェーンマネジメントシステム開発プロジェクト
- IoT を活用した地域防災システム開発プロジェクト
- 首都圏の稠密気象情報提供システム開発プロジェクト
- 長岡サテライトの活動
-
No.205(2019年) 国家レジリエンス研究推進センター
(2.7MB)
特集記事
- 逃げ遅れによる死者ゼロ、広域経済の早期復旧を目指して
- 大規模災害を力強くしなやかに乗り越えるために
- 避難・緊急活動支援統合システムの研究開発
- 衛星データ等即時共有システムと被災状況解析・予測技術の開発
- 広域経済の減災・早期復旧支援システム
- 線状降水帯の観測・予測システム開発
- 緊急時における判断力・対応力の向上を目指して
-
No.204(2019年) 平成30年度成果発表会「生きる、を支える科学技術
(1.9MB)
特集記事
- 生きる、を支える科学技術
- 雪国の情報革命 ~雪おろシグナル~
- 水蒸気噴火研究のいま
- 災害時情報集約支援チーム(ISUT)の取り組み
- 平成30年7月(西日本)豪雨から学んだこと
- 安平町での生活再建支援連携体の活動
- 今さら聞けないSIP4D のすべて 災害時の情報共有とは!
- 「生きる、を支える科学技術」が生まれるまで
-
No.203(2018年) 今季の災害について
(2.6MB)
特集記事
- 防災科研の災害対応
- 逆断層と横ずれ断層型が混在する大阪府北部の地震
- 平成30年北海道胆振東部地震
- レーダー観測から見る平成30年7月豪雨
- 平成30年7月豪雨による土砂災害の特徴
- 災害時情報集約支援チーム「ISUT」が始動!
- 災害状況の見える化
- 2018年の噴火を振り返る
- 平成30年冬期の大雪による被害
-
No.202(2018年) 研究開発の国際展開
(4.4MB)
特集記事
- 防災科学技術により世界のレジリエンス強化へ
- SDGs(持続可能な開発目標)の推進
- 「微動観測による広域地盤特性評価」の国際標準化
- タイ王国産業集積地のArea-BCM 体制の構築に向けて
- 日本の防災の知見を海外へ
- 防災と環境を両立させる蛇籠技術の開発
- 雪氷防災実験棟を用いた国際共同研究
-
No.201(2018年) 災害情報の共有
(5.4MB)
特集記事
- 社会実装に一歩近づいた5年間
- 津波遡上即時予測による津波被害軽減に向けて
- 局所発生する積乱雲を30秒で立体観測
- 発災後10分で被害を推定し配信
- 状況認識統一の「仲介役」として多組織間の情報共有を実現
- 現場からトップまで、すぐに使える情報を提供
- 長年の研究成果が着実に実った5年間
-
No.200(2018年) 硫黄島特集
(1.9MB)
特集記事
- 硫黄島での火山観測研究の概要
- 硫黄島の火山観測網
- 硫黄島の地殻変動
- 硫黄島の火山形成史
- 硫黄島の地震活動の研究
- 硫黄島の最近の噴火活動
- 硫黄島におけるカルデラ火山の研究
-
No.199(2018年) 雪氷特集
(2.0MB)
特集記事
- 雪氷災害の変遷と防災科研の取り組み
- 長岡サテライトでの雪氷防災研究センターの活動
- 雪氷防災実験棟の20年間の運用実績と今後の展望
- 吹雪発生予測システムの実証実験
- 着雪氷予測システムの実証実験
- レーダーからの雪の降水強度推定
- 長岡における降雪粒子観測
- 上越サイトにおける固形降水国際比較観測
- 積雪変質モデルによる雪崩発生予測
- 雪氷の非破壊計測手法について
- ネパール・ゴルカ地震となだれ
- 低気圧による降雪が原因の那須岳表層雪崩
-
No.198(2017年) 産業界との連携
(1.7MB)
特集記事
- 研究成果の活用を目指した知的財産ポリシーの制定 ~産業界との連携~
- 産業との連携による気象災害軽減
- 株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの連携と他分野への波及
- 気象レーダー分野における産業界との連携
- 計測震度の即時概算方法の開発と利用
- 地震で揺れない技術を目指して
-
No.197(2017年) E-ディフェンス特集
(2.1MB)
特集記事
- E-ディフェンスの維持管理、活用状況について
- 地盤-構造物連成試験体の震動台実験
- ため池堤体の耐震安全性に関する実験研究
- 基準等の整備に関わる研究への協力
- E-ディフェンスでの次世代RC造建物実験
- 体育館などに敷設される吊り天井の地震による脱落メカニズムの研究
- 数値震動台開発と映像の利活用について
- 地震災害に対する強靭性向上への貢献
- まとめ
-
No.196(2017年) 2016年の災害対応特集
(4.0MB)
特集記事
- 平成28年(2016年)熊本地震
- 熊本地震におけるリアルタイム被害推定
- 災害時の多様な情報を集約し、発信する
- 2016年8月の台風被害について
- 2016年10月8日の阿蘇中岳第一火口の噴火
- 2016年10月鳥取県中部の地震
- 2016年11月22日の福島県沖の地震
- 今冬の雪氷災害
-
No.195(2017年) 研究事業センター特集
(2.4MB)
特集記事
- 気象災害軽減イノベーションセンターのビジョンと取り組み
- 首都圏の稠密気象情報提供システム開発
- 大雪対応サプライチェーンマネジメントシステム開発とIoTを活用した地域防災システム開発
- 気象災害軽減イノベーションセンターの半年間
- 火山研究推進センターの発足
- 各種火山観測データの一元化
- 火山活動把握のための遠隔観測技術の開発
- シミュレーションによる噴火ハザード予測
- 火山災害対策技術の開発
-
No.194(2016年) 気象災害の監視技術特集
(2.0MB)
特集記事
- 雷の監視・予測技術の高度化への試み
- 浸水の監視・予測技術
- 土砂災害に対する観測技術の最前線
- 西表島網取湾での強大台風下の海洋観測
- 集中豪雪監視システム
- 雪氷災害の現況把握・監視技術について
-
No.193(2016年) 第4期特集
(1.5MB)
特集記事
- 防災科学技術研究所の第4期中長期計画
- 4期にむけての地震津波防災研究
- 火山災害の観測予測研究
- 実大三次元震動破壊実験施設等研究基盤を活用した地震減災研究
- 水・土砂災害の軽減に向けた研究開発計画
- 多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融合研究
- 自然災害のリスク評価と情報の利活用
- 効果的な災害対応の実現に向けて