お知らせ
日本地震学会若手学術奨励賞受賞
汐見勝彦主任研究員が、「レシーバ関数解析に基づく詳細なフィリピン海スラブ形状の解明」により、日本地震学会若手学術奨励賞を受賞しました。
受賞理由
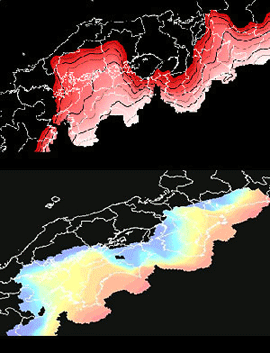
受賞者は、防災科学技術研究所の高感度地震観測網Hi-netのデータの解析に取り組み、とりわけレシーバ関数解析によるフィリピン海スラブの形状についての研究は、幅広い分野から注目されている。より客観的なレシーバ関数の推定のための多変量自己回帰モデル法や、P波速度構造の変化にも対応可能な速度インバージョン法の開発より、伊予灘から東海地域までのフィリピン海スラブの詳細な形状を求めた。
非地震性のスラブが中国山地下まで存在すること、四国の西部ではスラブ内地震活動が海洋性地殻内であるのに対して中部・東部では海洋マントル内で発生していること、スラブ内地震の活動分布・メカニズムはスラブの形状・相対的移動方向と高い相関があることなどが、明らかになった。また、モホ面の形状から大陸性下部地殻と海洋性地殻が接する領域を特定し、それが1946年南海地震ですべり量が大きな部分に対応することや、スラブの尾根の部分で伊勢湾や紀伊水道で深部低周波微動が非活発であることも明らかにした。
このように、多様な地震の震源過程と地下構造の密接な関係を具体的に示し、今後の多くの研究への指針を与えた。さらに、地震の観測研究を主体的に担う若手研究者としての一面も評価したい。Hi-netなどの地震波形デジタルデータの公開は、日本の地震学の発展において大きな転機で、今に至るまで多くの研究者が恩恵を享受している。候補者は、各観測点の地震計設置の方位推定も含めた信頼できるデータの構築と保守を高いレベルで維持し、公共へのデータ提供の仕事に取り組みながら、上述の成果を挙げた点は極めて重要である。
担当研究者のコメント
フィリピン海スラブは南海地震などを引き起こす元凶と考えられていますが、これまでその素性はあまり分かっていませんでした。今回、海溝型巨大地震解明の第一歩に、フィリピン海スラブに関する一連の研究や防災科研Hi-netのデータが役立っていると評価頂いたことを嬉しく感じるとともに、データ生成にご協力頂いております関係の皆様に大変感謝しております。Hi-netで収録されたデータには、「地震防災」や「地球科学」を語るうえで重要な情報がまだたくさん埋もれています。今後も高品質なデータを提供し続けられるように、またその性能を誇示できる研究成果を継続して発信出来るように頑張っていきたいと思います。引き続き、皆様のご協力・ご支援をよろしくお願いいたします。
