お知らせ
若月研究員が日本地形学連合奨励賞を受賞
水・土砂防災研究部の若月強研究員が日本地形学連合奨励賞を受賞し、11月13・14日に埼玉県熊谷市(立正大学熊谷キャンパス)で開催された地形学連合秋季大会において授賞式が行われました。
本賞は、過去3年間に雑誌「地形」に筆頭著書として論文を著した40歳未満の会員で、その中から優れた論文を執筆した若干名に対しておくられるもので、今回は2007~2009年に発行された「地形」を資料として受賞者が選考されました。
対象論文
若月 強,松倉公憲(2008)
二,三の花崗岩山地の表層崩壊地における土層形成速度の推定と崩壊周期, 地形,29,351-376.
若月 強,飯田智之,松四雄騎,小暮哲也,佐々木良宜,松倉公憲(2009)
泥質岩の風化特性が土層形成・斜面崩壊・斜面形状に与える影響:2003年台風10号により北海道日高地方で発生した斜面崩壊の事例, 地形,30,267-288.
受賞理由
若月・松倉(2008)は、4種類の花崗岩斜面の表層崩壊地において、拡散方程式による風化モデルを用いて、岩質による土層形成プロセスの差異を議論し、土層回復時間(崩壊周期)を推定した。その結果、花崗岩斜面の崩壊地における土層形成プロセスは、岩質の違いによって、拡散型と側方流型に分類することができることを指摘した。従来から、表層崩壊の崩土となる土層は風化(残積)土と運積土により構成されていることが指摘されているものの、その構成比率に関してはほとんど明らかになっていなかった。本論文では風化土の割合が大きい可能性があることを示した。
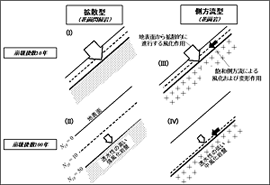
若月ほか(2009)は、崩壊規模の異なる2種類の泥質岩斜面において、泥質岩の風化特性と土層構造・斜面崩壊・斜面形状との関係を検討した。その結果、泥質岩斜面の土層構造や斜面崩壊の規模は、岩石の乾湿風化による細粒化のしやすさに強く影響を受けていることを明らかにした。岩質と土層構造・斜面崩壊との関係には未だ不明瞭な部分が多いが、本論文は2地域の比較を通してその解明を目指した研究である。

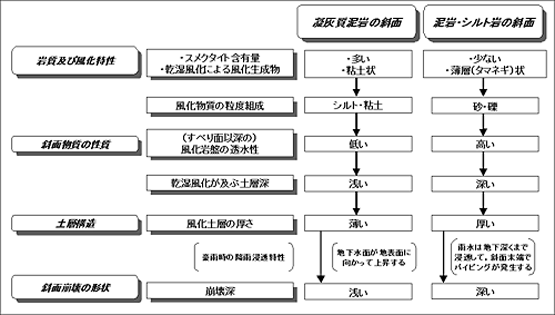
以上2編の論文は、斜面崩壊地の土層形成プロセスに関してロックコントロールの観点から新しい知見をもたらした研究であり、研究奨励賞に値すると判断される。
