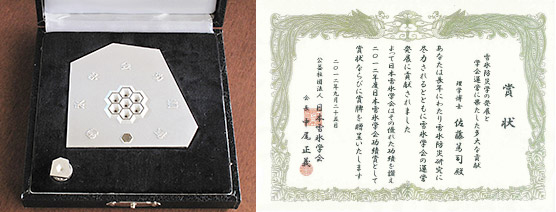受賞一覧
公益社団法人日本雪氷学会の学会賞を受賞しました
雪氷防災研究センターの新庄支所、 山口主任研究員、佐藤(篤)研究参事が、公益社団法人日本雪氷学会の学会賞を受賞し、2012年9月23日から27日に広島県福山市で開催された雪氷研究大会 (日本雪氷学会と日本雪工学会の合同大会)で授賞式が行われました。
技術賞
技術賞:(独)防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター 新庄支所
件名:多目的低温実験装置の技術開発およびその雪氷防災研究への応用
理由:(独)防災科学技術研究所は平成9年3月、雪氷防災研究センター新庄支所に「雪氷防災実験棟」を設置した。この実験施設では、雪氷圏の任意の環境を再現することが可能である。平成23年度までの15年間に実施された実験研究の総計は400件以上に達し、学術的、応用的に優れた研究成果が多数あげられている。多目的低温実験装置の技術開発を通じて実験雪氷学とでもいうべき分野を切り拓き、産学官の緊密な連携のもとに、雪氷学や雪氷防災に関わる研究を著しく発展させ、その功績は日本雪氷学会技術賞に値する。(日本雪氷学会の受賞理由より抜粋)
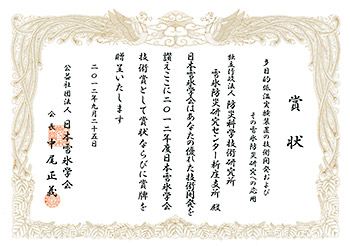
平田賞
平田賞:山口 悟主任研究員・博士(環境科学)
件名:不飽和条件下における積雪内部の水移動過程の解明とそのモデル化
理由:不飽和条件下における積雪内部の水移動過程は、水分を含む積雪の変化を明らかにする上で大きな課題である。山口 悟氏は、温度を0℃に保つ高精度の恒温槽を独自に設計し、積雪特性(雪質、粒径、密度)の異なる数多くの種類の積雪に対して水分特性の測定を行い、その積雪特性依存性を定式化した。次いで、積雪の不飽和透水係数を直接的に測定し、積雪特性および水分特性の関数として定式化した。これら一連の研究により、積雪の不飽和透水過程のモデルを初めて構築するとともに、積雪内部の不飽和透水過程の理論的解釈を可能とした。この成果は世界で最も利用されている積雪変質モデルSNOWPACK(スイス雪・雪崩研究所)に採用され、国内外で全層雪崩の研究などに利用されている。これにより、積雪内部の水の移動の再現性や全層雪崩・融雪災害などの湿雪型災害の予測精度が向上することから、今後の発展が期待されるため日本雪氷学会平田賞に値する。(日本雪氷学会の受賞理由より)
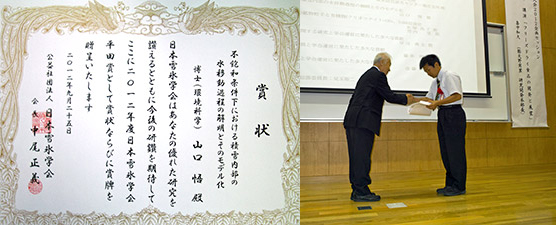
- 主要参考論文
-
Yamaguchi, S., K. Watanabe, T. Katsushima, A. Sato, T. Kumakura, 2012, Dependence of the water retention curve of snow on its characteristics. Annals of Glaciology, 53, (in print).
山口 悟,渡辺晋生,石井吉之, 2012. 積雪内部の水の移動に関する実験的研究.日本水文科学会誌,42.(in press)
Yamaguchi, S., T. Katsushima, A. Sato, T. Kumakura, 2010, Water retention curve of snow with different grain sizes. Cold Regions Science and Technology, 64. 87-93.
功績賞
功績賞:佐藤篤司研究参事・理学博士
件名:雪氷防災学の発展と学会運営に果たした多大な貢献
理由:佐藤篤司氏は、1999年に「標準雪を用いた雪の微細構造と熱伝導の研究」で日本雪氷学会学術賞を受賞し、その他寒地技術賞や東北雪氷学術賞などを受賞するとともに著しい成果を挙げた。その後、新庄支所長、長岡雪氷防災研究所長となり、「雪氷災害の発生予測に関する研究」を立ち上げ、そのプロジェクトリーダーとして活躍した。これらの研究は2006年度「日本雪氷学会技術賞」、そして「中越地震後の雪害軽減に関する日本雪工学会との合同委員会活動」で特別功績賞を受賞した。一方、1999年から日本雪氷学会理事となり、「雪氷」編集委員長や北信越支部長及び日本雪氷学会学術委員長と副会長を務め、学会の発展に貢献した。2010年には国際雪氷学会を札幌で開催し、現地実行委員長を務め成功に導いた。さらに、翌2011年には長岡市で雪氷研究大会を実行委員長として開催し、消雪パイプ誕生50周年事業とも連携した特色のある全国大会とした。一方、NHKの「アインシュタインの眼」や「クローズアップ現代」等に出演し、雪氷の幅広い紹介や雪害の解説を分かり易く行い、一般の人々に雪氷の基礎や重要性を啓蒙した功績は大きい。佐藤篤司氏は雪氷学の基礎に基づいて雪氷防災の研究を発展させると共に、学会の運営に果たした貢献も多大であり、日本雪氷学会功績賞に値する。(日本雪氷学会の受賞理由より抜粋)