受賞一覧
雪氷技術賞を受賞
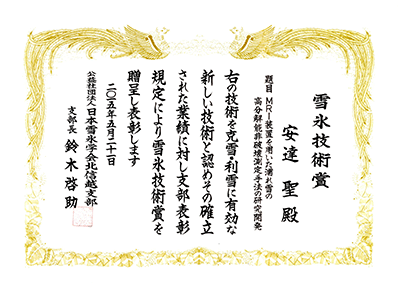
雪氷防災研究センターの安達聖特別研究員が「MRI装置を用いた濡れ雪の高分解能非破壊測定手法の研究開発」で雪氷技術賞を受賞しました。
雪氷技術賞は、克雪・利雪に有効な新しい技術を確立したものに与えられる賞です。
安達聖特別研究員が確立した「MRI装置を用いた濡れ雪の高分解能非破壊測定手法」が克雪・利雪に有効な新しい技術と高く評価され、受賞につながりました。
授賞式は平成27年5月21日に長野県松本市で開催された2015年度 北信越支部総会および研究発表会・製品発表検討会で行われました。
受賞標題
MRI装置を用いた濡れ雪の高分解能非破壊測定手法の研究開発
受賞理由

北信越を含む本州の雪害を考える上で濡れ雪の詳細な物理特性の把握は非常に重要であるが、これまでの測定はバルク的な観点からのものに留まり、積雪微細構造とその中での水の挙動を議論する精度には至っていない。乾き雪に関しては、欧米を中心にX線 CT を使った積雪微細構造と物理特性との関係に関する研究が近年精力的に進められているが、同装置では水と氷を区別できないという弱点があった。
こうした中で安達氏は、MRI(磁気共鳴画像法)が物質を非破壊で精査できる点に注目し、同装置を導入した北海道教育大学尾関研究室において大学院時代からこれを雪氷研究に応用する研究を行ってきた。MRI 装置が X 線CT と大きく異なるのは、物質内の水の挙動を直接検知できる点である。ただ主に医療分野で使われているMRI 装置を雪氷分野への研究に応用するためには、温度変化によって静磁場均一性が劣化すること、空間分解能を上げると勾配磁場コイルからの発熱が氷試料に影響を与えることなどの解決すべき課題があった。安達氏は、それらの問題を解決するために、2 次シムコイルを適切に調節して磁場のゆがみを補正することおよび装置内の発熱をおさえるための空冷システムの開発を行い、実際に改良を行った低温室MRI が着氷構造の研究や積雪内部の水の存在に関する研究に有効なことを示した。
防災科研・雪氷防災研究センターに移ってからは、MRI 装置内で水と雪が共存する 0℃の環境を長時間保つための装置の開発と高分解能化、測定時間の短縮化を精力的に進め、高い分解能で濡れ雪測定を可能にする高分解能雪氷用MRI を設計し開発した(雪氷防災研究センター新庄雪氷実験所に導入済)。この中では、MRI 装置による非破壊含水率の測定手法を開発し、積雪の吸水過程並びに排水過程の水分特性曲線の測定を行い、積雪内部の水みちの発達を考える上で重要な“ヒステリシス”が積雪に存在する可能性を示唆する成果をあげている。
以上のように安達氏の開発、研究を行っているMRI 装置を用いた濡れ雪の高分解能非破壊測定手法は世界でも先進的な研究であり、従来バルクでしか議論されてこなかった濡れ雪の物理特性研究にとって画期的な測定手法である。その測定手法および技術を反映した高分解能雪氷用MRI 装置は、今後積雪内部の詳細な水の移動モデル等を研究する際に有効なデータを取得可能にするだけではなく、全層雪崩や着雪氷などの湿雪災害のメカニズム解明にも役立つことが期待され、雪氷技術賞受賞者に選定した。
受賞コメント
このたび受賞させていただきました湿雪に対応した雪氷用MRIの研究は、雪氷防災研究センターで勤め始めてから本格的に始めたものです。この雪氷用MRIの研究開発で蓄積されたデータと技術を生かし設計された1.5T雪氷用MRIは新庄雪氷環境実験所に導入されています。雪氷用MRIと同時期に導入された雪氷用μ-CT装置を併用することで、より詳細な積雪の3次元構造を把握し、将来的に雪氷災害 の防止につながるよう努力していきたいと考えています。
