受賞一覧
平成29年度東北雪氷賞(学術賞)を受賞
雪氷防災研究部門の根本征樹主任研究員が、平成29年度東北雪氷賞(学術賞)を受賞しました。
東北雪氷賞(学術賞)は、雪氷学の発展に貴重な貢献を与える研究をなした者で、学会誌に掲載論文を有する者に与えられる賞です。今回の受賞は、根本征樹主任研究員の、吹雪の基本的な性質に関する研究を進展させた功績ならびにそれを予測システムに実装し吹雪災害の再発防止に貢献した功績が、高く評価されたものです。
授賞式は平成29年5月12日に岩手県立大学アイーナキャンパスで行われました。

受賞題目
- 吹雪の発達と風速分布に及ぼす降雪の影響に関する研究
-
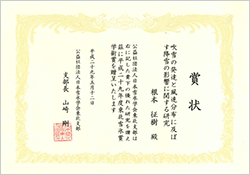
根本征樹会員は、雪氷防災実験棟において降雪の有無による詳細な吹雪の風洞比較実験を行い、これと数値計算の結果を比較した。すなわち、温度-10℃で硬い雪面と軟らかい雪面で降雪がある場合と無い場合をそれぞれ風速を変化させて実験するとともに、同様の条件で自ら組み立てた雪粒子の気流に対する影響を加味した接地境界層の乱流モデルを用いて風速分布の数値計算を行い、両者を比較した。
この結果、軟らかい雪面の場合は風速を大きくすると降雪が無くとも発生するが、降雪があると吹雪が発達し易くなることを確かめた。これは乱流モデルにおいては、吹雪発生時の臨界摩擦速度が小さくなることを意味する。また、雪粒子はその周りの空気の運動に影響するものの、風速分布には大きな変化が見られなかった。
これらは従来から定性的に知られていたことではあるが、風洞実験・数値計算の両面から定量的に確認された意義は大きい。今後はこれらの温度依存性の研究が期待される。また同会員は、これまでの吹雪発生モデルの知見に基づいて、2013年3月に猛吹雪により5名の死者を出した北海道中標津町において、吹雪予測システムを構築した上、試験的に運用することにより、同町から多大な信頼を得ている。
以上のことから、吹雪の基本的な性質に関する研究を進展させた功績ならびにそれを予測システムに実装し吹雪災害の再発防止に貢献した功績を評価し、同会員を東北雪氷賞学術賞に推薦する。
受賞コメント

日本国内の雪氷研究において歴史のある日本雪氷学会東北支部より、この度、東北雪氷賞(学術賞)を頂くこととなり、大変光栄に思います。私がこれまでに実施してきました吹雪研究において、当初、降雪が無い場合のいわゆる地吹雪を対象として、メカニズム解明を進めてきました。これは、研究開始時において、地吹雪の頻度が比較的多く見られる北海道に所在していたことが大きな理由と言えます。
しかしながら、東北地方を本拠地として吹雪研究を発展させるにあたり、野外における実際の吹雪の状況を目にすると、降雪を伴う、もしくは降雪に起因して吹雪が発達するような状況が度々見られ、吹雪の素過程において降雪が及ぼす影響を詳しく調べなければならない、と思いを新たにした次第です。幸い、防災科学技術研究所雪氷防災研究センターの雪氷環境実験室(研究開始当時は新庄支所)には、人工降雪装置を備えた雪氷防災実験棟が設置されており、かつ比較的大型(測定部長さ14 m、断面1 m×1 m)の風洞装置も備えられていたことから、これらの施設をフルに活用した吹雪・降雪実験の実施が可能である等、置かれた研究環境において大変恵まれており、こうした実験について比較的スムーズに進めるとともに、モデル化に関する研究にも資することが出来ました。
吹雪のメカニズムについて、一見、風により雪粒子が飛ばされて舞うだけの単純な構造として見なされることが多いかもしれません。しかしながら、その実態は、様々な相互作用(大気乱流と雪粒子、雪粒子と雪面など様々)や乱流による乱れの効果、雪粒子の粒径分布の効果、(そして本課題においてメインとなる)降雪粒子・降雪片の影響など、多数の要素が互いに影響しあう、非常に複雑な現象であると言えます。特に私の吹雪研究の黎明期において考慮しなかった降雪の影響について、比較的温暖で積雪表層の雪粒子の可動性が低い東北・北陸地方の吹雪においては、その発生・発達において降雪が極めて重大な影響を及ぼすほか、そうした影響が降雪の種類(降雪種。雪結晶の複合体からなる降雪片なのか、もしくはあられなのか、など)によっても変わるなど、地吹雪のみでも十分複雑な吹雪現象において、その取扱いの困難さを一層高める効果を有します。このような深遠な現象について、全容の解明に至るには程遠い状況ではありますが、これからも、野外で生じている自然現象そのものを注意深く観察し、現象の多様性・地域性なども丁寧に取扱い、現象解明および防災への貢献を目指していきたいと思います。
上述した研究テーマのほか、雪氷防災研究センターで開発を進めている「雪氷災害発生予測システム」のサブシステムである「吹雪発生予測システム」について、2013年度より、北海道道東地方の中標津町周辺にて、試験運用・実証実験を実施する機会が得られました(文部科学省の委託事業「地域防災対策支援研究プロジェクト」の助成によります)。当該地域は発達した低気圧の影響による猛吹雪・暴風雪の発生頻度が高く、またなだらかで開けた地形かつ樹林帯が少ないなど、強い吹雪に至りやすい地形でもあるため、吹雪の研究に携わるものとして、何とか地域の吹雪対策・災害防止に役立ちたい、と思っていた場所でした。この取り組みは今後も継続して実施する予定ですが、現地自治体で防災を担当されている方々の熱意、意欲は極めて高く、上記システムの試験運用およびそれに基づくシステム高度化について多大な貢献を頂いております。また研究者側からの押しつけでなく、自治体側が能動的に情報を活用するなど、双方向の、協働による協力体制が構築されつつあります。こうした連携が、防災研究成果の地域での活用について一過性のものでなく、地域に根ざした継続性のあるものとして進化をもたらすと確信しております。
最後に、本研究の推進に当たり、雪氷防災研究センターの職員をはじめとする防災科研の皆様、さらには学会等で議論を深めてくださった研究者仲間や、予測モデルの試験運用にご協力くださった様々な方々(民間企業、行政、自治体などで防災等に関わる方々)など、大変多くの方々による有形無形のご助力を頂いております。この場を借りて心より感謝申し上げます。
